さんすう
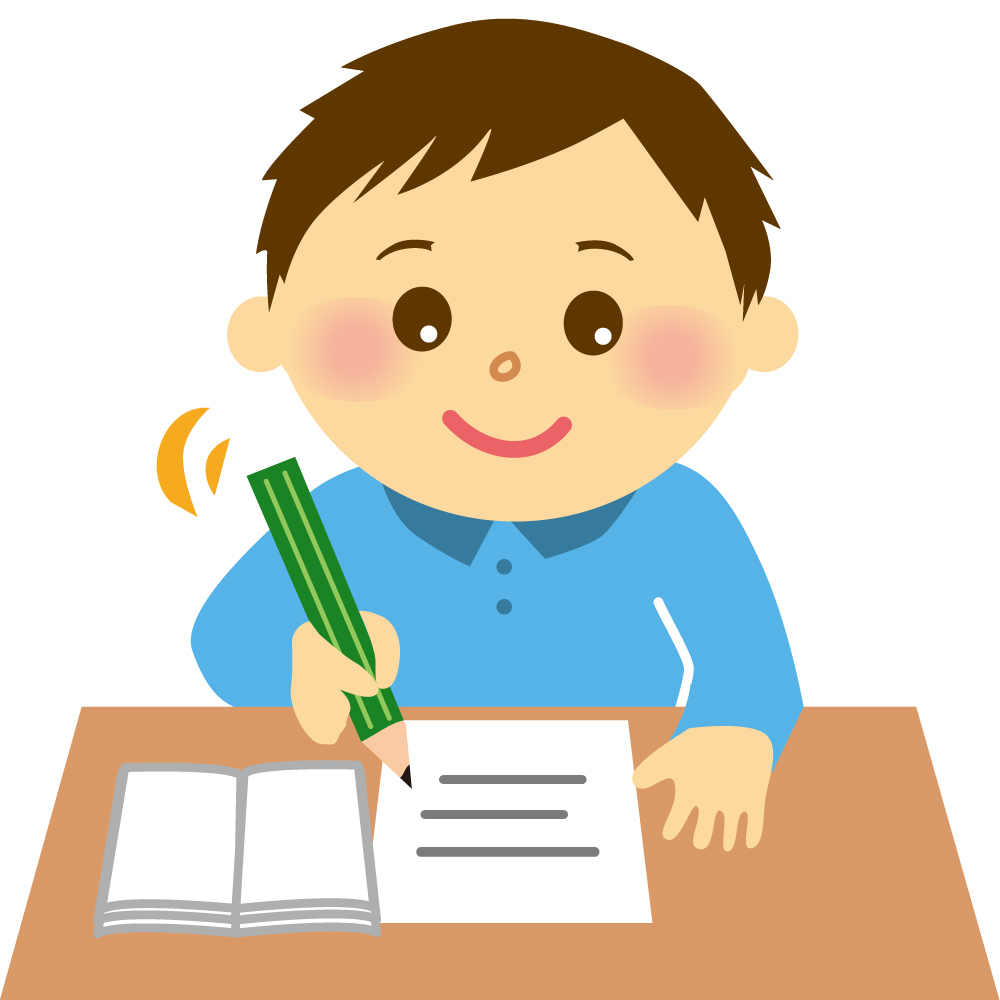
子どもが小学校に入学してから早数か月が過ぎ、
宿題なるプリントを持ち帰ってくるようになりました。
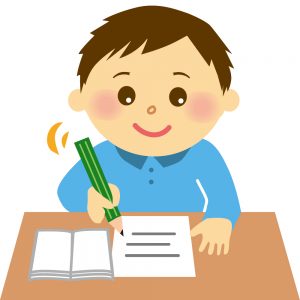
とある休日に子どもが算数の宿題をやっていたので、
「わからいところがあったら聞いてね」
と気軽に声をかけたつもりが、
すぐに教えて欲しいと言われ、一緒に宿題をすることになりました。
内容は小学1年生の内容なので、
回答内容に困ることは無かったのですが、
”どうしてそういう答えになるか”
を教えるのが非常に難しいと痛感させられる出来事がありました。

その時は、
机の上に飴玉が3個あって、
一つ食べたら飴玉は何個になる?
という例にして説明をしたのですが、子どもの回答は「3個」。
その理由を聞くと、
「だって口の中に1個飴玉があるでしょ。机の上の2個と合わせたら3個でしょ」
「・・・」
まさかの例題に対する盲点を付いてくるとは、恐るべし小学生。
すぐに「机の上の~」を付けたして説明したところ、内容は理解してもらえました。
知ってる人にしてみれば、説明しなくても当たり前と思うことも、
知らない人からしてみれば、何が当たり前なのかすらわからない。
説明を求められている以上は、
内容を省くことなく伝えてあげるべき、
など改めて分からないことを説明する難しさを痛感した休日でした。

